|
空から見た法隆寺の伽藍
石守廃寺もこのような姿だったのでしょうか
石守廃寺とは
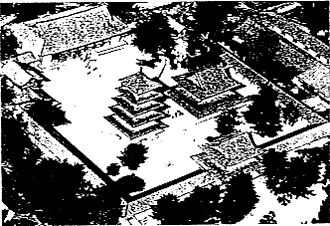 神野町石守のこの地は、付近の田畑に瓦が散らばり、塔の心礎(しんそ)(塔の中心柱の礎石)が残っていたことから古代寺院があったことが知られていました。この寺院は今から約1300年前の奈良時代、奈良の都平城京が造られたのと同じころに造られ、百数十年後の平安時代にはつぶれてなくなったようです。寺院の名前、いつ誰が造ったのかについて言い伝えや記録は何も残っていません。そこでこの遺跡は、石守にある無名の寺院の遺跡ということで、「石守廃寺」と呼んでいます。 神野町石守のこの地は、付近の田畑に瓦が散らばり、塔の心礎(しんそ)(塔の中心柱の礎石)が残っていたことから古代寺院があったことが知られていました。この寺院は今から約1300年前の奈良時代、奈良の都平城京が造られたのと同じころに造られ、百数十年後の平安時代にはつぶれてなくなったようです。寺院の名前、いつ誰が造ったのかについて言い伝えや記録は何も残っていません。そこでこの遺跡は、石守にある無名の寺院の遺跡ということで、「石守廃寺」と呼んでいます。
石守廃寺は過去に3度発掘調査が行われ、金堂(こんどう)(仏像を安置した建物)と塔の基礎などが見つかっています。寺院の主な建物にはこの他に講堂(こうどう)(お坊さんが学問する建物)があります。これらの寺院の主要な部分を構成する建物の配置を伽藍配置(がらんはいち)といいます。
石守廃寺は塔と金堂が東西に並ぶ配置になっていますが、これは西条廃寺と同じで、法隆寺と似た伽藍配置になります。
発掘調査で何がわかったか
☆寺院ができる前にムラがあったことがわかりました。
古墳時代から飛鳥時代の竪穴住居と建物が見つかりました。寺院が造られるまでこの地にはムラが営まれていたようです。また弥生時代以前の石器も数点見つかっています。この地は古くから人々の生活の場だったことがわかります。
☆伽藍のまわりの様子がわかりました。
寺院の東端で東門と思われる施設を、さらにその東側で別院と思われる区画を発見しました。別院の区画内には四角く巡る溝があり、たくさんの瓦が投げ込まれていました。溝の内側は地面が熱で赤く焼けています。溝のまわりには建物などがあったようです。
今回、講堂と思われる建物を発見しました。その北側にはお坊さんの生活した建物(僧坊(そうぼう))があります。この建物は県内でも屈指の大型建物です。
僧坊付近からは食器やナペなどの土器が出ています。また工房もあったようで、鍛冶(かじ)に用いるフイゴや坩堝(るつぼ)などが見つかっています。
僧坊と考えられる建物の発見により、石守廃寺ではお坊さんが常時生活していたことが確実になりました。また伽藍のまわりの様子がこれほど明らかになった例はあまりなく、今後古代の地方寺院を研究する上で貴重な資料を提供することでしょう。
遺構から見つかったもの
たくさんの瓦が見つかりました。寺院の屋根には下図のように色々な種類の瓦があります。しかし今回見つかった瓦は不要になり捨てられたものであるため、すべての種類の瓦が出土している訳ではありません。また残り具合もよくありません。瓦には作る時に布を当てたあとが表面に残っていることから布目瓦(ぬのめかわら)と呼んでいます。見つかった瓦のほとんどは平瓦、丸瓦ですが、ごく少量軒先を飾る丸瓦(軒丸瓦(のきまるかわら))がありました。軒丸瓦には蓮の花や同心円の模様が描かれています。
瓦の他に寺院に伴うものとして、土器、鉄釘、銅製金具があります。銅製金具には唐草模様が描かれています。
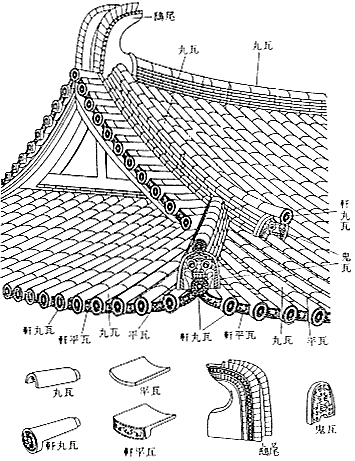 |
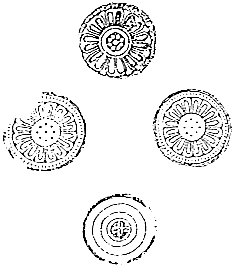
石守廃寺の軒丸瓦
|
|