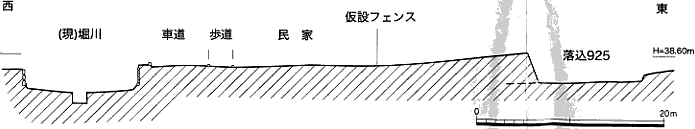平安京左京三条二坊十町(へいあんきょうさきょうさんじょうにぼうじゅっちょう)
(元城巽中学校(もとじょうそんちゅうがっこう))
現地説明会
2007年7月28日(土)
財団法人 京都市埋蔵文化財研究所
※このページの写真、文、図は、すべて当日配布の現説資料からの転載です。
目次
はじめに
今回の説明は、桃山時代の遺構を中心に行います。残念ながら当時の状況を示す資料は残っていませんが、室町時代には妙顕寺(みょうけんじ)が調査地の東隣に移されたことがわかっています。ところがこの寺は、天正(てんしょう)11年(1583)には羽柴秀吉(はしばひでよし)(豊臣(とよとみ)秀吉)によって破脚(はきゃく)され、その跡に妙顕寺城(みょうけんじじょう)が建てられました。妙顕寺城は、天正15年に衆楽第(じゅらくだい)が完成するまでの京都の中心を担った城でした。また、慶長(けいちょう)8年(1603)に二条城(にじょうじょう)ができると、元和9年(1623)にこの地を土井利勝(どいとしかつ)が拝領し土井藩邸となりました。さらに、明治5年(1872)からは城巽小学校となりました。
遺構
北西部で落込(おちこみ)925を検出しました。幅10m、東西12m以上、深さ1.1mあり、調査地を超えてさらに西に延びます。南側にはやや小規模な落込920も並んでいます。落込925の底には薄くきめ細かい泥が堆積しており、かつては水がたまっていたことがわかります。
その後、これらは砂礫を含む土を入れて一気に埋め立てられていました。泥の層とその上に入れられた土からは桃山時代の終わり頃から江戸時代はじめ頃の遺物がみつかりました。
ちょうど二条城から土井屋敷が造営される時期にあたります。
遺物
落込925からみつかったものには、多数の土器類(土師器(はじき)・施釉陶器(せゆうとうき)[瀬戸(せと)・美濃(みの)・唐津(からつ)]、焼締陶器(やきしめとうき)[備前(びぜん)・信楽(しがらき)・丹波(たんば)]、外国の陶磁器(とうじき)[朝鮮・中国])や瓦類があります。この他に木製品(漆器椀(しっきわん)・箸(はし)・下駄(げた)・櫛(くし)・刷毛(はけ)の柄(え))や獣骨(じゅうこつ)(鹿・猪・犬)など多彩のものがあります。
これらの中には焦げ付いた土師器の浅鉢や、調理した断痕のある鹿・猪の骨など生活感あふれるものも含まれています。
 浅皿 |
 落込925 |
 落込925 桃山時代後期〜江戸時代初め |
 落込925 |
 落込1080 桃山時代後期〜江戸時代初め |
まとめ
- みつかった落込925は水がたまっていた痕跡があり、調査区の西側へ延びていることから 堀川に開口していると考えられます。
- 堀川の周辺には中・近世を通じて水運を利用した材木商が多数存在したことが文献資料に 残されています。発見した遺構はそうした人々に利用された船人(ふないり)あるいは木場(きば)(材木を貯蔵する場所)ではないかと考えています。
図1 平安京条坊と調査地(●印)(『角川日本史辞典』より)
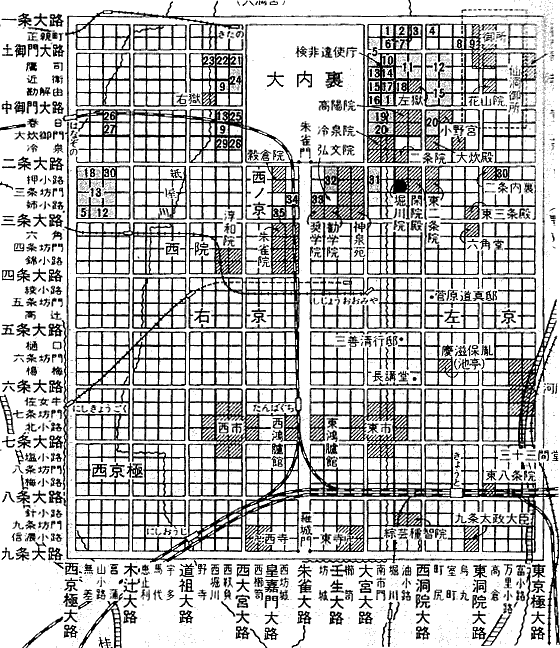
図2 左京三条二坊内での調査位置図(1:5,000)
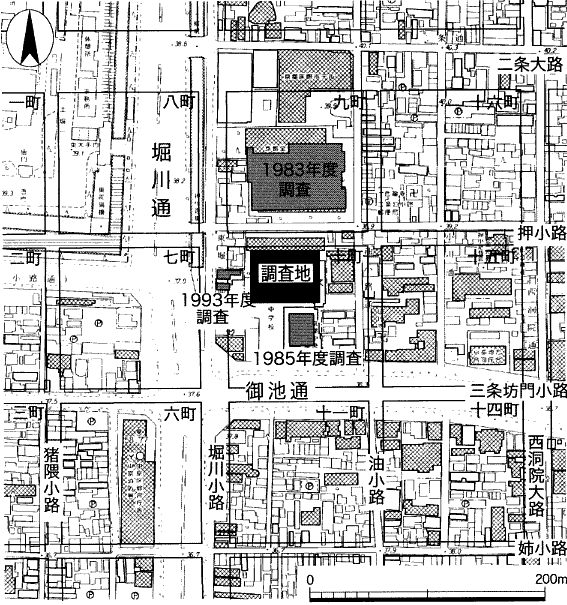
図3 桃山〜江戸時代初期の京都と調査地(『京都の歴史4』付図より)
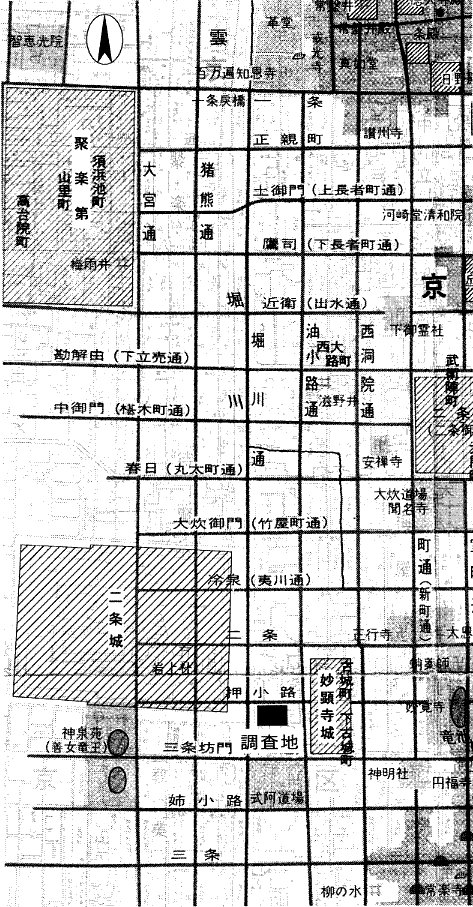
図4 『寛永後万治前洛中絵図』の調査地(1642年頃成立)
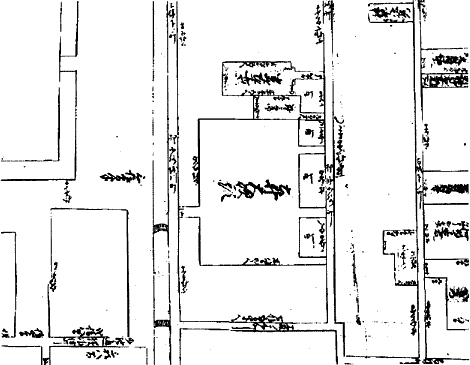
図5 主要遺構配置図(1:300)
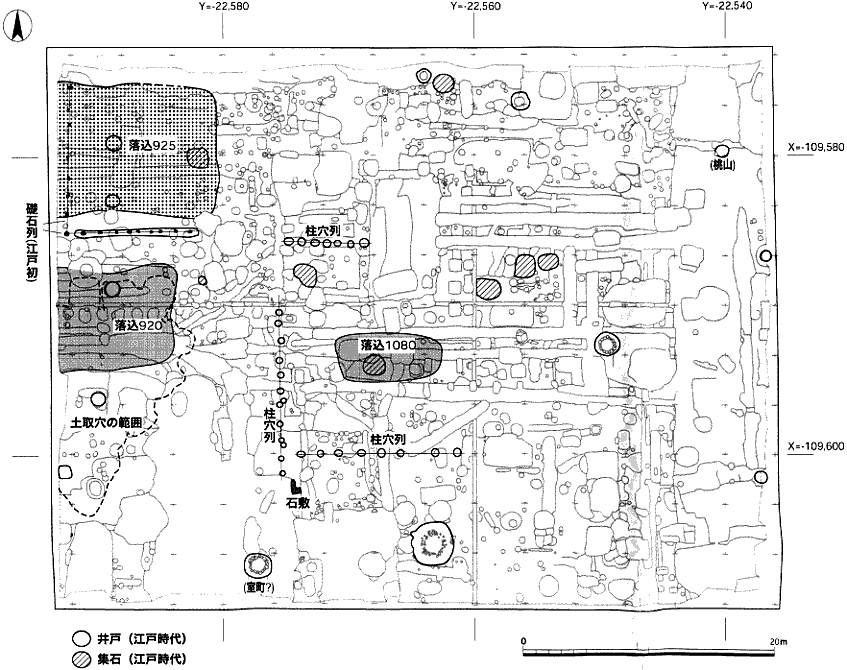
図6 落込925 平面・断面実測図(1:200)
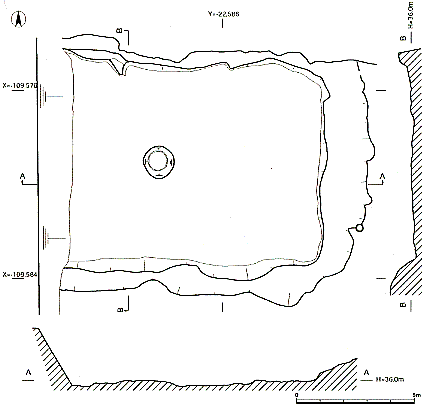
図7 現在の堀川と落込925の起伏断面模式図
(※現堀川断面は調査地の北約70m地点を測り、高低差0.7mを調整した)